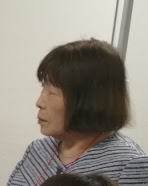2025年度看護管理塾第2章「マネジメントに取り組む」を終えて
ファシリテーター 井部俊子
昨年からこの章を担当しました。今回は内容は変更せず、構成を第1部、第2部、第3部としました。本論に入る前に、ヘルシンキで開催されたICN大会への参加報告を、2枚の写真を添えていたしました。一枚目は中国の看護師たちの大集合写真、もう一枚の写真は、こどもを抱き学会に参加しているパパさん看護師の姿です。では、本論に入りましょう。
第2部はマネジャーになっていくプロセスです。マネジャーの仕事とは、〈物事を成し遂げる〉(Getting things done)+〈他者を通して〉(through others)であるという中原理論を説明しました。〈他者を通して〉ということは「自ら動かないこと」が求められていること、さらに、成し遂げる「物事」を明確にしておく必要があることを指摘しました。したがって、マネジャーになるということは、「実務担当者時代に身につけた知識やスキルをマネジャー用に変更することや、場合によってはそれらを捨て去ること」であるのです。
今回の研修では、「リーダーが本当に語るべきこと」(エイミー・ジェン・ス:Diamond
Harvard Business Review,編集部訳,April 2025,80‐83)を追加しました。それらは、①自分のキャラクターに正直に語る、②文脈を踏まえて語る、③明快さをもって語る、④相手を知ろうとする、⑤相手とのつながりを求めて語ることです。さらに、「威厳」「コミュニケーション」「外見」がエグゼクティブプレゼンスの要素であり、リーダーらしさを表象していることも紹介しました。
第3部はマネジャーの挑戦課題です。7つの挑戦課題(中原,2,021)を説明したのち、まず各人が困難度を判定し、次にチームでの困難度を評定してもらいました。チームで高得点であった項目をとり上げて、その対策を議論して発表してもらいました。
各チームがどの項目を「高い困難」としたかを以下に示します。
部下育成は、Eチーム、Kチーム
目標咀嚼は、Gチーム
政治交渉は、Bチーム、Cチーム
多様な人材活用は、なし
意思決定は、Fチーム
マインド維持は、Aチーム、Dチーム、Hチーム、Iチーム
プレマネバランスは、Jチーム
でした。
各チームが対策を議論して、ホワイトボードに記述し、メンバーが渡り歩いて意見交換をしつつ精度を高めました。看護リカレント教育部News Letterでその様子をご覧下さい。
井部 俊子